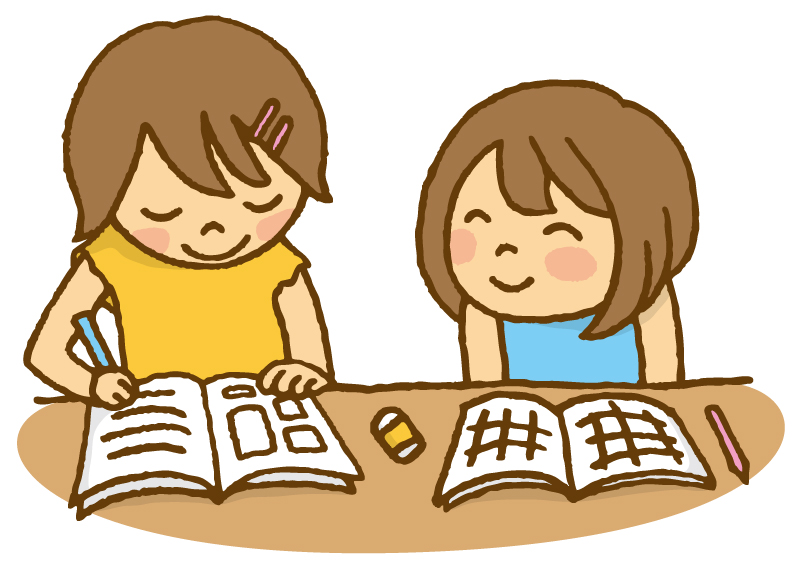
- 子どもの習い事に公文をしようと思っているけど、効果あるのかな?
- 月謝が高いけど、タブレット学習より良いの?
- 公文の弊害があるって聞いたけど・・・
このように公文を習わせるべきか、または継続するべきか、悩んでいませんか?
実は公文の「真の効果」は学力向上ではなく、非認知能力の向上であることをご存じですか?
公文の「真の効果」を理解したうえで公文を習わせる、または継続するか否かを判断することが重要です。
理解せず公文をしてしまうと、中途半端にやめて、時間とお金を無駄にしてしまいます。
私は公文を5歳から初めました。公文歴10年です。引っ越しも多く、様々な教室を経験しました。加えて、長女と長男も3歳から公文に通っています。物心ついたころから接点があり、酸いも甘いも知っています。
この記事では、そんな公文通の私が公文の「真の効果」について説明します。
この記事を読むことで、公文の「真の効果」を知らぬまま公文を習い、時間とお金を無駄にしてしまう可能性が低くなります。

これを知っているか知らないかで、公文学習が成功するかどうかが全然違いますよ!
本ページはプロモーションを含みます。
公文の真の効果は学力向上ではない!他でもない非認知能力の向上であることを理解すべき!
公文の「真の効果」は「非認知能力の向上」です。
基礎学力だけでなく、以下の非認知能力を向上させることができます。
- 忍耐力:粘りずよく最後まで頑張る力
- 自己肯定感:やり抜く力、自分を信じる力
- 意欲:集中力、学習習慣
- セルフコントロール:自制心、精神力
公文に期待している効果は何ですか?学力ですか?
もちろん学力も向上します。
でも学習塾のような「学校の成績を上げたい」とか、「試験に受かりたい」とかを期待するのであれば、やめた方が良いです。遠回りです。効率よく対策できる学習塾に行きましょう。
公文はひたすら基礎学力(道具の使い方)を学び、上記の非認知能力を養う場所です。応用力(モノづくり)を期待してはいけません。モノづくりはモノづくりを教えてくれる場所で学びましょう。ちなみに応用力を養うのであれば、RISU算数などが有名です。
RISU算数↑今ならクーポンコード「msm07a」で1週間お試しの限定キャンペーン実施中です。(※上限人数達し次第、早期終了の可能性あり)
公文の壁を乗り越えた「成功体験」こそが、公文の「真髄」!
それでは、なぜ公文で非認知能力が向上するのかについて説明します。
ご存じの通り、公文は反復練習による基礎学力の向上を目指します。他の学習塾と比較にならない量の反復練習です。
例えば、足し算だけで約500枚のプリントがあります。1枚のプリントには平均20問あるので、問題数は約10,000問です。
で、これをひたすら反復練習します。
正確性とスピードの両方が求められます。それも1枚当たり2分までなど、小さな子どもには厳しいレベルです。
正確性とスピードのどちらかがNGだと、数か月かけて、もう一回初めからやります。
2回でクリアすることは少なく、私の経験上、5回、6回はよくあることです。
結果、初めは順調に学習していた子どもでも、いつまでも終わらない莫大な問題の反復に嫌気がさしたり、難しい問題につまづいて、スランプに陥ります。
そして、
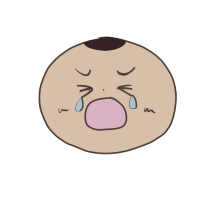
「公文嫌だー----!」
と公文の壁がふさがるのです。
公文の壁は子どもだけでなく、親にとっても分厚い壁です。
高いお月謝払っているのに、全然進まない・・・
子どもも宿題しなくなり、イライラ・・・
親も子どもをきつく叱ってしまい、さらに子どもは公文が嫌になる悪循環。
このままでは勉強嫌いな子になってしまいそう・・・やめた方が良いのかな!?
もう・・・
ダメだーーーーーーーーーーッ!!!!!
どっかーーーーーーーー----ん!

ここです!!
ここで、公文の壁を越えるか、越えないかが、大きな分かれ道となります。
もう少し子どもを信じて何とか踏ん張ってください。
公文の壁を越えた子どもはこの高い壁を越えることで「成功体験」を得ます。
この体験によって子どもは
「どんなに大変でしんどくても、粘り強く最後まで頑張れば、いつか出来るようになるんだ!」
ということを身をもって学ぶのです。
そして冒頭にお伝えした以下の非認知能力が向上します。
- 忍耐力:粘りずよく最後まで頑張る力
- 自己肯定感:やり抜く力、自分を信じる力
- 意欲:集中力、学習習慣
- セルフコントロール:自制心、精神力
大きな壁であればあるほど、得られる能力も大きくなります。
反復練習→スランプ(公文の壁)→乗り越える(成功体験)→非認知能力の向上→・・・そしてまた新たな反復練習→スランプ・・・
そしてこの循環を繰り返すことで、ぐんぐん非認知能力を高めることができるのです。これが公文式学習です。
小さな子どもがこの壁を越えるには、親の強い覚悟が必要です。
公文は親のサポートが必須だからです。
とくに幼児期は親が子どもを励まし慰め奮い立たせて、一緒に壁に立ち向かう必要があります。
ちなみに子どもが非認知能力を高めた結果、いつか自分一人で乗り越えられる日が来るようになります。そうなると親のサポートは不要です。
あなたはこの公文の壁を越える自信がありますか?
壁を越える自信がなければ、公文はやめた方が良いです。公文の壁を越えられず、「真の効果」を得ないまま、時間とお金の無駄になります。
長女で経験した「公文の壁」と「成功体験」
長女の公文の壁の例をお話しします。
長女が公文を始めたのは3歳から。
長女は国語と算数の二教科をしています。算数3Aクラスの足し算(たす1)でつまずき、公文の壁を経験しました。
詳細はまた別の記事にしたいと思うので割愛します。
半年以上、たす1を何度も何度もやり続けるけども、なかなかスピードが目標10分を切らず。
「算数は嫌い!もう嫌だ!」と泣きながら言うように。
モチベーションも下がり続ける娘を見て、公文に慣れていた私もこのままで良いのだろうか?という迷いが出てきました。

自分が経験してきた「公文の壁」と親の立場で経験した「公文の壁」は全くの別物でした・・・!
分かっていても、きっつい!
結局、壁を越えるのに時間がかかりましたが、2年後の今は「算数大好き!」と言ってくれています。
最後まで頑張ってやれば出来る(忍耐力)、自分なら出来る(自己肯定感)、をしっかり学んだ彼女は本当に成長しました。
公文も自分から取り組むようになり、宿題も自分から10枚に増やしてほしいと言うほどです。( ;∀;)

それを聞いた私は嬉しさで泣いた!
学習習慣がついただけでなく、集中力・忍耐力・自制心もずいぶん鍛えられました。
公文をして良かったです。
タブレット学習では体験することはできなかったと思います。
公文の弊害について
ネット上の弊害は公文の真髄を理解していない人の意見
おそらくここまで読んで、でも公文にもネットに上がっているような弊害があるんでしょ?というご意見があるかもしれません。
公文の弊害についても別記事にしたいと思うので、ここでは多くは記載しません。
ただ個人的な意見としては、公文の真髄を理解しないままやめてしまった人や、そういう子どもをみた人の意見なのかなと感じます。
公文信者といって見下す記事もあり、残念でなりませんが・・・(私もここまで公文してるから公文信者であることは違いないやろうけど(^^;))。
まぁ客観的な意見としては、弊害ばかりで効果がなければ、ここまで全国にくもん教室は広まっていないと思います。
「真の効果」を得るために注意すること
真の効果を得るために、いくつか注意することを記載します。
公文の壁を乗り越えるには親のサポートが必須
公文は普通の塾と違います。親のサポートが必須です。
前述の通り、特に初めは公文の壁を乗り越えるために子どもを励まし、一緒に立ち向かう必要があります。
非認知能力が高まるにつれて、一人で壁を乗り越えられるようになります。それまでは親も時間と労力を費やすことになります。
ちなみに、共働きだからといって公文をあきらめる必要はありません。
我が家も残業が多いフルタイム共働きです。ですが、何とか頑張っています。
大事なのは、覚悟です。
先生の質にばらつきが大きいため、教室選びはしっかり行う
同じ公文でも、学習方針や教育の仕方は教室の先生によって大きく変わります。質の良い教育を提供してくれるところもあれば、悪いところもあります。もちろん相性もあります。子どもと先生の相性が悪いと公文の壁を乗り越えることが困難になります。
家から近いという理由だけでなく、しっかりと教室選びを行いましょう。
教室の選び方も別記事にしたいと思います。
幼児期に通い始め、出来れば5年(少なくとも3年)は続ける
出来れば幼児期3歳から5歳までの間に通い始めるのが良いと思います。
理由は早ければ早いほど、非認知能力(特に学習意欲、学習習慣)を身に着けやすいからです。
また繰り返しますが、公文はじっくり時間をかけて基礎学力(道具の使い方)と非認知能力を向上させる場所です。
出来れば5年、少なくとも3年は継続しないと、身につきません。
なので、幼児期に公文を習い始め、5年以上継続して基礎学力と非認知能力を身に着けた後、小学校高学年以降にやめるのが良いと思います。その後は前述のRISU算数や学習塾などで応用力を存分に磨いてください。ネット上でささやかれている弊害はほぼないのではないかなと思います。
RISU算数まとめ:公文は「公文の壁」を乗り越え、真の効果である"非認知能力"を獲得するまで続けよう
この記事のまとめです。
公文の真の効果は「非認知能力の向上」です。
基礎学力だけでなく、以下の非認知能力を向上させることができます。
- 忍耐力:粘りずよく最後まで頑張る力
- 自己肯定感:やり抜く力、自分を信じる力
- 意欲:集中力、学習習慣
- セルフコントロール:自制心、精神力
この非認知能力の向上ためには、以下の循環を繰り返す必要があります。
反復練習→スランプ(公文の壁)→乗り越える(成功体験)→非認知能力の向上→・・・そしてまた新たな反復練習→スランプ・・・
公文学習は、この公文の壁を乗り越えるという成功体験を通じて、ぐんぐん非認知能力を高めることができます。
ただし、小さな子どもがこの公文壁を越えるには、親の強い覚悟が必要です。
この覚悟がないと、公文を中途半端にやめることとなり、「真の効果」を得ないまま、時間とお金の無駄になります。
これを理解したうえで、公文を習わせるべきか、または継続するべきかをご検討いただければ幸いです。
最後までお読みいただきまして有難うございました。
